運動は人生を好転させる
「こんな当たり前なことを」と言われそうですが私が思っていた以上に運動は身体にも心にもいい影響を与えるらしいのです。
私は現在リハビリの仕事をしています。体を動かすことで患者さんの身体機能向上の期待ができるのはもちろんですがリハビリ直後の表情もすこしすっきりしている印象を受けます。
私もバドミントンを趣味で行っていますが、終わった後は晴れやかな気分になります。
それは嫌なことがあった後も同様で嫌なことを忘れるということではなく把握した状態で嫌な気持ちが軽減しているといったイメージです。
現在ストレス社会とよく言われています。ストレス解消法は様々あると思いますが、暴飲暴食や散財等自分へダメージを与えることを行うのであれば、空いた時間を確保し運動をしてみてください。運動のストレスに対しての好ましい影響はすでに報告されています。
定期的に有酸素運動をすると体のコンディションが安定するので、ストレスを受けても、急激に心拍数が上がったり、ストレスホルモンが過剰に出たりしなくなる。少々のストレスには反応しないようになるのだ。
引用 NHK出版 脳を鍛えるには運動しかない! 最新科学でわかった脳細胞の増やし方
また認知症に対しての運動療法も推奨されています。
運動量によって女性たちを五グループに分けた。最も活発に運動していたグループは、記憶力テストと一般的な知能テストで、老後に能力が衰える確率が二〇パーセント低かった。
引用 NHK出版 脳を鍛えるには運動しかない! 最新科学でわかった脳細胞の増やし方
他にも多くの運動による身体への効果が報告されています。受験生やストレスを抱えた方、高齢者等(疾患のある方は主治医への確認は必要です)も各々のできる範囲で運動を行ってほしいと思います。
とはいうものの運動は継続することが大切なのですが、そこが一番難しいとも感じます。いざ始めたものの1週間後にはもうやめていることはよくあります。やめる理由は無数にあるので自分を納得させることはいとも簡単にできてしまいます。
今回は現役の理学療法士である私が趣味のランニングや、リハビリで患者様のモチベーションを上げて運動を継続させるよう工夫している点を紹介します。
少しだけやってみる
例えば自分の中で3km走ると決めて習慣として行っていたところ今日はなんだかやりたくないと感じることがあるでしょう。
そんなときは「今日は1kmにするか」とハードルを低くして少しだけやってみるのです。もちろん本当に体がしんどいときは無理する必要はないです。
しかし少しだけやってみると、運動している最中にやっぱりもっとやってみようと意欲が湧き出てくるのです。そして1km走るつもりが実際には3km走っていたという具合になります。やる気とはやる前から出るのではなくやっていると出てくるのだと感じます。
目標を細かく分ける
あなたがフルマラソンを完走したいとしましょう。このときいきなり42.195㎞を目標にするのは現実的ではありませんし、すぐにモチベーションが失われてしまいます。まずは5㎞、次に10㎞と細かく目標を分けて最終的に42.195㎞を走れるように練習しますよね。
これは全ての運動にも当てはまります。また私の仕事でもあるリハビリでも同じです。
このときに大切なことは
- 具体的な数値で目標を設定する
- 無理をしない範囲で目標を設定する
- 目標達成後のご褒美を用意する
やはり数値化して進行が目に見えるとやってる感が出てモチベーションに繋がります。
また強度に関しては個人的にはややきついかなくらいが継続しやすいです。ちゃんとキツイと次やりたくない気持ちが出てきてしまいます。またリハビリで使う尺度に自覚的運動強度(ボルグスケール)というものがあり、こちらでも楽〜ややきつい程度が医学的根拠に基づき推奨されています。
ボルグスケールでの11.「楽である」から13.「ややきつい」程度に当たり、生活習慣病の予防などの効果が得られて安全に行える運動強度とされています。
引用 健康長寿ネット
ご褒美はモノでなくても褒める等の精神的なものでも効果があります。特に子供の場合は褒めなければ、次回も努力しようとは思いません。また自分で自分を褒めてあげるのも以外と大切なことですね。
他の人と一緒に行う
運動を一人だけで行おうとするとどうしても
「今日は休みたい」「明日がんばろう」
という気持ちに負けてしまいます。
他の人と約束することで半ば強制的に運動をしなければならない環境になりますし
また一緒に行うことで運動を楽しんで行えるようになります。
でも大人になって一緒に運動する友達なんていないよ(TT)
という人が大半ではないかと思います。
私がおすすめするのはオンラインのレッスンです。
プロのトレーナーが付き添って教えてくれるため初心者でも安心して運動ができます。
オンラインであれば主婦の方も忙しい合間をぬって参加できますし、雨や雪などの天候にも左右されずに参加できますので継続がしやすいと感じています。
無料体験できるサービスもありますのでぜひご活用ください。
さいごに
今回は運動を継続するポイントについて紹介しました。
皆様も参考にしていただき、運動を継続し健康維持を目指して下さい。
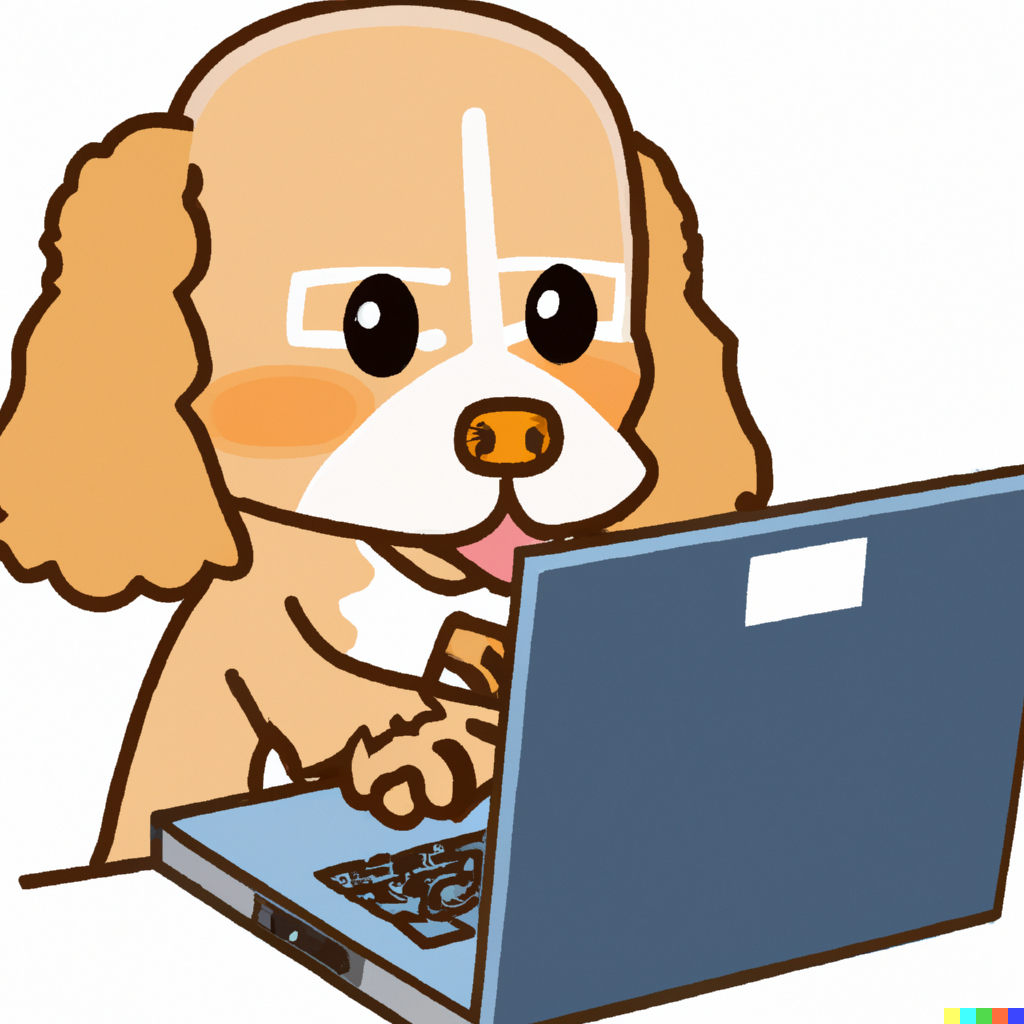
国立大学の理学療法学科を卒業後、回復期病院や老人保健施設で勤務。福祉住環境コーディネーター2級。ファイナンシャルプランナー3級。趣味は読書。子育てしながら有益な情報を投稿出来るよう日々努力しています。





コメント